【衝撃】渋沢栄一の“成功哲学”は深谷にあった!「論語と算盤」が示す“稼ぎながら徳を積む”禁断の秘訣

「近代日本経済の父」と称される渋沢栄一。新一万円札の顔としても、その名を知らない人はいないでしょう。約500もの会社設立に関わり、約600もの社会公共事業や教育機関を支援した稀代の事業家であり、社会活動家です。
彼の偉業は多岐にわたりますが、その根底には常に一貫した哲学がありました。それが、彼の著書名にもなっている「論語と算盤」です。多くの人が「道徳」と「経済」は相容れないものと考えがちですが、渋沢栄一はこれらを一体として捉え、「稼ぎながら徳を積む」ことこそが、真の豊かさと社会の発展につながると説きました。
では、この独自の成功哲学は、一体どこで培われたのでしょうか? その答えは、彼の生まれ故郷である埼玉県深谷市にあります。深谷の地で育まれた価値観と学びこそが、「論語と算盤」の思想の源流なのです。
この記事では、渋沢栄一の「論語と算盤」に込められた思想を深掘りし、それがどのように深谷の地で育まれ、彼の成功へと繋がったのかを探ります。そして、現代にも通じるその「稼ぎながら徳を積む」秘訣を、深谷にある渋沢栄一記念館の見どころと共にご紹介します。
渋沢栄一とは? 深谷に生まれた「近代日本経済の父」
渋沢栄一は、天保11年(1840年)、現在の埼玉県深谷市血洗島(ちあらいじま)の豊かな農家に生まれました。家業は藍玉の製造・販売や養蚕で、幼い頃から商売の実際を肌で感じながら育ちました。
特筆すべきは、彼が幼少期から学問に励んだことです。特に、隣村に住む従兄である尾高惇忠(おだか じゅんちゅう)のもとで学んだ『論語』は、彼の生涯の思想的基盤となります。惇忠は、栄一にとって学問の師であると同時に、人間的な成長を促す重要な存在でした。
青年期には尊王攘夷思想に傾倒し、一時は過激な計画に加わろうとしますが、惇忠の弟である長七郎の説得で断念。その後、一橋家に仕える機会を得て、財政改革などで手腕を発揮します。そして、徳川慶喜の弟・昭武の随員としてパリ万国博覧会へ渡欧。ここで彼は、ヨーロッパの先進的な産業や社会制度、特に株式会社制度を目の当たりにし、大きな衝撃を受けます。
帰国後、明治新政府に招かれ官僚となりますが、やがて民間の立場で日本の近代化を推進することを決意し、大蔵省を辞任。第一国立銀行(現在のみずほ銀行の前身)を設立し、これを拠点に、製紙、紡績、鉄道、海運、ガス、電力など、多岐にわたる分野で近代的な企業を次々と立ち上げていきました。
彼の活動は経済分野にとどまらず、東京大学や日本女子大学校などの教育機関、東京養育院(現在の東京都健康長寿医療センターの前身)などの社会福祉施設、さらには国際親善にも尽力しました。その生涯はまさに、日本の近代化そのものと言えるでしょう。
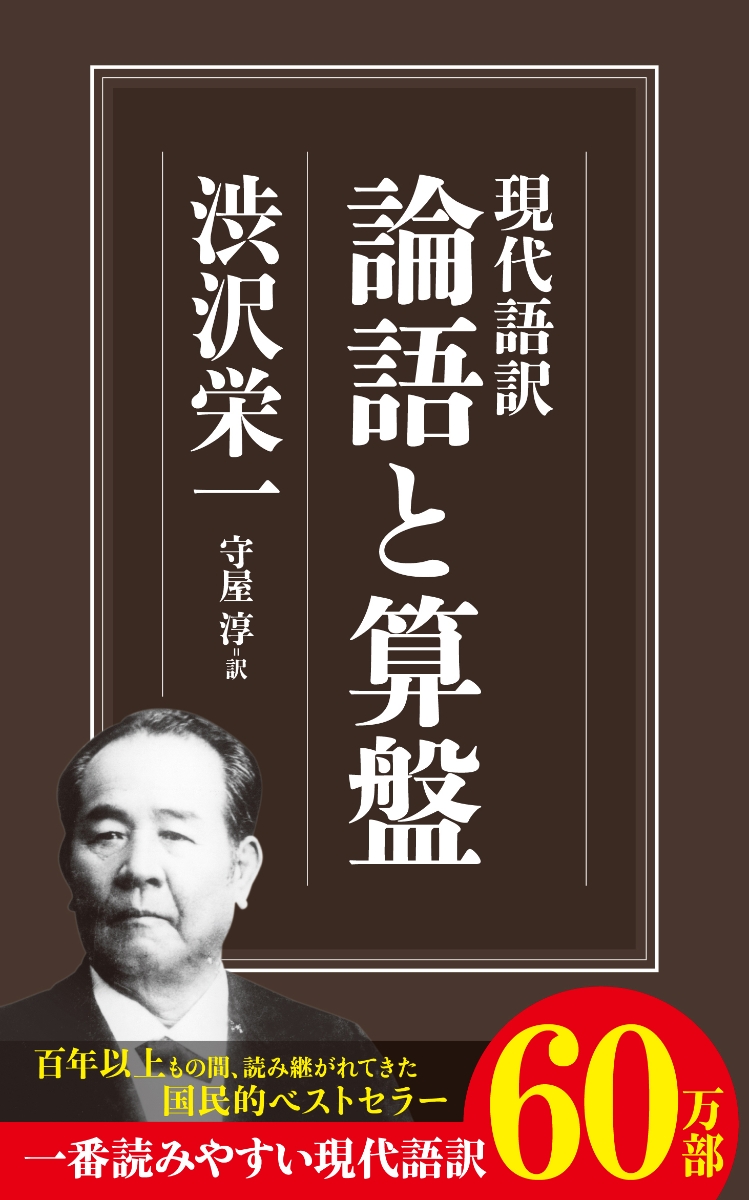
「論語と算盤」に込められた思想:道徳と経済は一体である
渋沢栄一の哲学の核心は、「論語と算盤」に集約されています。これは、単に『論語』を読んで道徳を学び、そろばんで計算して利益を出す、という単純な話ではありません。
彼が提唱したのは「道徳経済合一説」です。これは、「仁義道徳」と「生産殖利」、すなわち「道徳」と「経済活動」は決して対立するものではなく、むしろ一体となって進むべきであるという考え方です。
当時の日本では、儒教の影響もあり、「士農工商」の身分制度の中で商売は卑しいものと見なされがちでした。また、「仁すなわち富ならず。富すなわち仁ならず。」(仁者は富まず、富者は仁ならず)という言葉に代表されるように、お金儲けと道徳は両立しない、儲けようとすれば道徳を忘れ、道徳を重んじれば利益は薄くなる、という考え方が根強くありました。
しかし、渋沢栄一はこれに異を唱えました。彼は、尊敬する孔子の教えを深く理解し、孔子が戒めたのは「道徳に反した不義の利益」であって、「道徳に適った正当な利益」はむしろ奨励されるべきだと考えたのです。
彼は、経済活動によって利益を生み出すことは、国を富ませ、国民を豊かにするために不可欠な行為であり、それは孔子の「博く民に施して、能く衆を済う」(広く民に施して、よく衆を救う)という言葉にも通じる、社会貢献そのものであると捉えました。
ただし、その経済活動は、私利私欲のためだけに行われるべきではなく、常に高い倫理観、すなわち『論語』に説かれる仁義道徳に基づいている必要があります。道理にかなった方法で利益を追求し、その利益を社会に還元することで、自分自身も豊かになり、社会全体も発展していく。これが「稼ぎながら徳を積む」という彼の思想の真髄です。
彼は、経済学の祖とされるアダム・スミスもまた、倫理哲学の教授であり、『国富論』において道徳と経済の調和を説いていることを指摘し、「道徳・経済合一は東西問わずの世界中に適する不変の原理である」と確信していました。
「論語と算盤」は深谷でどう育まれたか
渋沢栄一の「論語と算盤」の思想が、なぜ深谷の地で育まれたのか。そこには、彼の生家の環境と、師である尾高惇忠の存在が大きく関わっています。
渋沢家は、単なる農家ではなく、藍玉の製造・販売や養蚕、さらには金融業(質屋)も営む、地域でも有数の豪農商でした。幼い栄一は、父市郎右衛門から家業の手伝いを通じて、商売の厳しさや面白さ、そして地域社会との関わり方を学びました。これは、彼の「算盤」すなわち経済活動の基礎を形成したと言えるでしょう。
一方で、彼は父から学問の手ほどきを受け、さらに尾高惇忠のもとで『論語』をはじめとする古典を学びました。惇忠は、単に知識を教えるだけでなく、人間としてどうあるべきか、社会にどう貢献すべきかといった精神的な側面を重視した教育を行いました。これは、彼の「論語」すなわち道徳・倫理観の基礎を形成しました。
深谷という土地は、江戸時代から農業が盛んな一方で、中山道が通り、商業も栄えた地域です。また、血洗島村は利根川の舟運も利用できる交通の要衝でもありました。このような環境で育った栄一は、生産活動(農業、養蚕)、製造業(藍玉)、商業、金融業といった多様な経済活動を身近に感じながら、同時に地域社会の結びつきや、そこで求められる倫理観を学んでいったと考えられます。
尾高惇忠との出会いは、特に重要です。惇忠は、栄一に『論語』の精神を深く植え付けました。単なる学問としてではなく、生き方、事業のあり方として『論語』を捉える視点は、惇忠から受け継がれたものです。惇忠自身も、富岡製糸場の初代場長を務めるなど、実業に関わった人物であり、理論と実践を兼ね備えていました。
深谷の豊かな自然、農業と商業が融合した経済環境、そして尾高惇忠という優れた師との出会い。これらが複合的に作用し、渋沢栄一の中に「道徳なき経済は野蛮であり、経済なき道徳は寝言である」という「論語と算盤」の思想が育まれていったのです。
「論語と算盤」を体感する:渋沢栄一記念館の見どころ
渋沢栄一の思想と生涯を深く理解するためには、やはり彼の故郷である深谷市を訪れるのが一番です。中でも、その中心となるのが渋沢栄一記念館です。
記念館では、渋沢栄一ゆかりの遺墨や写真、書簡など、貴重な資料が多数展示されている資料室と、最新技術で再現された渋沢栄一アンドロイドによる講義を見学できる講義室があります。
資料室:栄一の足跡をたどる
資料室では、栄一の幼少期から晩年までの生涯を、豊富な資料とともにたどることができます。彼の直筆の書や、設立に関わった企業の資料などを見ることで、その活動の広さと深さを実感できるでしょう。深谷での生い立ちや、尾高惇忠との関係を示す展示もあり、「論語と算盤」の思想がどのように形成されていったのかを具体的に学ぶことができます。
資料室の見学は無料ですが、10名以上の団体の場合は予約が必要です。個人や10名未満のグループであれば予約なしで見学できますが、混雑状況によっては入室を待つ場合があるとのことです。
講義室:アンドロイドが語る「道徳経済合一説」
渋沢栄一記念館の最大の目玉の一つが、本物そっくりに再現された渋沢栄一アンドロイドによる講義です。このアンドロイドは、ドトールコーヒー名誉会長の鳥羽博道氏の寄付により制作され、大正時代に栄一自身が語った「道徳経済合一説」を現代風にアレンジした内容で講義を行います。
アンドロイドが、当時の栄一の風貌そのままに、力強く「道徳」と「経済」の両立の重要性を説く姿は、まさに圧巻です。彼の思想が、単なる古い教えではなく、現代にも通じる普遍的な原理であることを肌で感じられる貴重な体験となるでしょう。
アンドロイド講義の見学は、人数にかかわらず事前予約が必須です。予約はインターネットの予約システムから、見学希望日の2日前まで可能です。予約システムが利用できない場合は、記念館に電話で問い合わせることもできます。講義開始後は入退室ができないため、予約時間の5分前までに受付を済ませるように注意が必要です。

渋沢栄一記念館 利用案内
- 開館時間:
- 資料室: 午前9時~午後5時
- 講義室(アンドロイド): 午前9時30分~午後4時30分(最終講義は午後3時30分から)
- 休館日: 年末年始(12月29日~1月3日)および臨時休室日(清掃・メンテナンス等による)
- 利用料金: 資料室、講義室ともに無料
- 予約:
- アンドロイド講義: 人数にかかわらず必須(見学希望日の2日前まで)
- 資料室: 10名以上の団体のみ必須
- 予約方法: 深谷市ホームページの予約システム、または電話(048-587-1100)
- アクセス:
- 電車: JR高崎線 深谷駅または岡部駅からタクシーで約16分
- 車: 関越自動車道 花園ICから約40分、本庄児玉ICから約30分 / 北関東自動車道 太田藪塚ICから約40分
- 駐車場: 建物南側に179台(大型バス可)
- 住所: 〒366-0002 埼玉県深谷市下手計1204
- 電話: 048-587-1100
※最新の情報や臨時休館日については、必ず深谷市公式ホームページをご確認ください。
論語の里を巡る:深谷で感じる栄一の息吹
渋沢栄一記念館だけでなく、深谷市には彼の生涯や思想に触れることができる場所が点在しています。これらの場所は「論語の里」と呼ばれ、栄一のルーツをたどる上で欠かせません。
- 旧渋沢邸「中の家(なかんち)」: 栄一が生まれ育った生家です。当時の暮らしぶりを知ることができ、彼の原点を感じられます。こちらも10名以上の団体は予約が必要です。
- 尾高惇忠生家: 栄一の師である尾高惇忠の生家です。ここで栄一は『論語』を学びました。栄一の思想形成に大きな影響を与えた場所です。こちらも10名以上の団体は予約が必要です。
これらの施設を巡ることで、栄一がどのような環境で育ち、何を学び、いかにして「論語と算盤」の思想を確立していったのかを、より立体的に理解することができます。深谷市では、「論語の里まち歩きツアー」なども開催されており、ガイド付きで巡るのもおすすめです。また、「論語の里」ガイドアプリなども提供されています。

現代に活かす「論語と算盤」:稼ぎながら徳を積む秘訣
渋沢栄一の「論語と算盤」の思想は、100年以上経った現代においても、全く色褪せていません。むしろ、企業の社会的責任(CSR)や持続可能な開発目標(SDGs)が重視される現代において、その重要性は増していると言えるでしょう。
彼の思想から、現代の私たちが「稼ぎながら徳を積む」ための秘訣をいくつか学ぶことができます。
- 目的意識を持つ: 何のために事業を行うのか、単なる利益追求ではなく、社会にどのような価値を提供するのかという高い目的意識を持つこと。栄一は、国を富ませ、国民を豊かにするという明確な目的を持っていました。
- 倫理観を基盤とする: どんなに儲かる話でも、道理や倫理に反することは行わない。常に公正さ、誠実さを重んじること。これが長期的な信頼と持続的な成功につながります。
- 公共の利益を追求する: 自分の利益だけでなく、従業員、顧客、地域社会、そして国全体の利益を考えること。公共の利益を追求することが、結果として自身の利益にもつながるという考え方です。
- 学び続ける姿勢: 栄一は生涯にわたって学び続け、新しい知識や技術を積極的に取り入れました。変化の激しい現代において、学びを止めない姿勢は不可欠です。
- 社会貢献を事業の一部と捉える: 社会貢献を特別な活動ではなく、事業活動そのものの中に組み込むこと。教育や福祉への支援を惜しまなかった栄一の姿勢は、現代のCSRやCSV(Creating Shared Value)に通じます。
これらの秘訣は、大企業だけでなく、中小企業や個人事業主、さらには私たち一人ひとりの働き方や生き方にも応用できるものです。「稼ぐこと」と「善く生きること」は別々のものではなく、両立し、互いを高め合う関係にある。これが「論語と算盤」が示す、時代を超えた成功への道なのです。
まとめ:深谷で「論語と算盤」の精神に触れよう
渋沢栄一の「論語と算盤」は、単なる古いビジネス書ではありません。それは、彼の生まれ故郷である深谷の地で培われた、人間として、そして事業家としての生き方の哲学です。
道徳と経済を両立させ、「稼ぎながら徳を積む」という彼の思想は、現代社会が直面する様々な課題に対する示唆に富んでいます。
深谷市にある渋沢栄一記念館を訪れ、アンドロイド講義で彼の言葉に耳を傾け、資料室でその足跡をたどることは、「論語と算盤」の精神を肌で感じる貴重な体験となるでしょう。さらに、旧渋沢邸「中の家」や尾高惇忠生家といった「論語の里」を巡ることで、彼の思想が育まれた原風景に触れることができます。
ぜひ一度、深谷を訪れて、渋沢栄一の「論語と算盤」に込められた“禁断の秘訣”を、あなた自身の目で、耳で、心で感じ取ってみてください。きっと、あなたの働き方や生き方に対する新たな視点が開かれるはずです。