小学校プログラミング教育の疑問を解消!保護者向けサポートとおすすめ教材
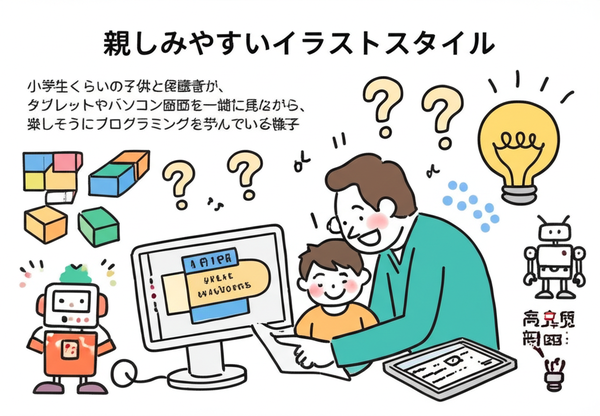
2020年度から小学校でプログラミング教育が必修化され、数年が経過しました。しかし、「プログラミングって難しそう」「うちの子にできるの?」「親としてどうサポートすればいいの?」といった疑問や不安を抱えている保護者の方も少なくないでしょう。
現代社会は急速にデジタル化が進み、AIやロボットが身近になる一方で、IT人材の不足も指摘されています。このような予測困難な時代を生き抜く子どもたちにとって、コンピュータを理解し、主体的に活用する力は不可欠です。小学校のプログラミング教育は、まさにこの力を育むことを目的としています。
この記事では、小学校プログラミング教育の目的や具体的な内容、保護者が抱きがちな不安とその解消法、そして家庭でできるサポートやおすすめの教材について、分かりやすく解説します。お子さんの学びをより豊かにするためのヒントとして、ぜひ最後までお読みください。
小学校プログラミング教育とは?必修化の目的と概要
「プログラミング」と聞くと、専門的な技術や複雑なコードをイメージするかもしれません。しかし、小学校で必修化されたプログラミング教育は、プログラマーを育成することが直接的な目的ではありません。
文部科学省の「小学校プログラミング教育の手引」によると、小学校段階のプログラミング教育の主なねらいは以下の3点です。
- プログラミング的思考を育む
- 「プログラミング的思考」とは、自分が意図する一連の活動を実現するために、どのような動きの組み合わせが必要であり、一つ一つの動きに対応した記号を、どのように組み合わせたらいいのか、記号の組み合わせをどのように改善していけば、より意図した活動に近づくのか、といったことを論理的に考えていく力です。
- 物事を順序立てて考え、問題を解決するための論理的な道筋を立てる力が養われます。
- 身近な問題の解決やより良い社会を築こうとする態度を育む
- コンピュータはプログラムで動いていること、コンピュータが日常生活のさまざまな場面で使われ、生活を便利にしていることに気づき、情報技術の利点や重要性を理解します。
- コンピュータを活用して身近な問題を解決したり、より良い社会を築こうとしたりする態度を育みます。
- 各教科等での学びをより確実なものとする
- 算数や理科などの授業の中でプログラミング体験を行うことで、各教科の学習内容をより深く、より確実に理解することを目的とします。
新しい教科ではない「プログラミング」
小学校のプログラミング教育は、「プログラミング」という独立した教科として新設されたわけではありません。算数、理科、総合的な学習の時間など、既存の教科や活動の中で、プログラミングの考え方や体験を取り入れる形で実施されます。
これにより、子どもたちは特定の技術を学ぶだけでなく、各教科で培う資質・能力とプログラミング的思考を結びつけながら、横断的に学ぶことができます。
アンプラグドからデジタルまで多様な学習方法
小学校のプログラミング教育では、必ずしもパソコンを使うわけではありません。特に低学年では、コンピュータを使わずにプログラミング的思考を学ぶ「アンプラグドプログラミング」が取り入れられることもあります。
- アンプラグドプログラミング: カードや身体を使ったゲーム、パズルなどを通して、順序立てて考えることや指示を正確に伝えることなどを体験的に学びます。
- デジタル教材: パソコンやタブレットを使用し、主にビジュアルプログラミング言語(ブロックを組み合わせてプログラムを作る言語)を使って、簡単なアニメーションやゲーム、ロボット制御などを行います。
これらの多様な方法を通じて、子どもたちはプログラミングの楽しさに触れ、基本的な考え方を身につけていきます。
なぜ今、小学校でプログラミング教育が必要なのか?
プログラミング教育が必修化された背景には、現代社会の大きな変化があります。
急速なデジタル化とIT人材不足
私たちの生活は、スマートフォン、家電、自動車、社会インフラに至るまで、あらゆる面でコンピュータとプログラムに支えられています。テレワークやオンライン授業の普及など、社会全体のデジタル化は加速する一方です。
一方で、経済産業省の調査では、今後IT人材が大幅に不足することが予測されています。このような状況に対応するため、コンピュータの仕組みを理解し、活用できる人材を育成することが喫緊の課題となっています。
AI時代に求められる力
AI(人工知能)やロボット技術の発展により、これまで人間が行っていた定型的な作業の多くが自動化されると予測されています。このような時代に、人間が社会で活躍し続けるためには、AIには代替できない創造性や、複雑な問題を解決する能力がより一層重要になります。
プログラミング教育で育まれる論理的思考力、問題解決能力、創造力は、まさにAI時代に求められる普遍的なスキルです。
将来の学びへの接続
プログラミング教育は、小学校だけでなく、中学校、高等学校でも段階的に充実が図られています。中学校では技術・家庭科で計測・制御やネットワークを利用したプログラミングを学び、高等学校では必修科目「情報I」でより本格的なプログラミングや情報活用について学びます。
さらに、2025年度からは大学入学共通テストに「情報I」が新設されます。小学校段階でプログラミングの基礎的な考え方に触れておくことは、将来の学習や進路選択においても大きなアドバンテージとなります。
小学校での具体的な学習内容と実践例
小学校のプログラミング教育は、学年や学校、地域によって取り組みが異なりますが、文部科学省の指導例などを参考に、各教科等で様々な実践が行われています。
学年別の取り組み例
- 低学年(1・2年生): 主にアンプラグドプログラミングや、直感的に操作できるビジュアルプログラミングツール(Viscuitなど)を使用し、物事を順序立てて考えることや、簡単な指示でキャラクターを動かす体験などを通して、プログラミング的思考の基礎を育みます。
- 例:プログラミング絵本でキャラクターに指示を出す、カードやビーズでパターンを作る、教室内でロボット役と命令役に分かれて動くゲーム。
- 中学年(3・4年生): ビジュアルプログラミングツール(Scratchなど)を活用し、簡単なゲームやアニメーション作成、ロボット制御などに取り組みます。繰り返しや条件分岐といった基本的なプログラミングの概念に触れ、試行錯誤しながら課題を解決する経験を重ねます。
- 例:漢字を分解・結合するプログラム、繰り返しのリズムを作るプログラム、プログラミングで操作できるロボットの作成。
- 高学年(5・6年生): 算数や理科などの教科内容と連携した、より発展的なプログラミング活動を行います。センサーを使った制御や、社会課題の解決に向けたアイデアをプログラミングで表現するなど、実践的な学びを深めます。
- 例:正多角形や小数の計算プログラム(算数)、電気の流れや効率的な使い方を考えるプログラム(理科)、敬語の使い方を考えるプログラム(国語)、動く模様の作成(図工)、地域課題解決のためのプログラム作成(総合)。
各教科での連携例
- 算数: 正多角形を作図するプログラムを作成することで、図形の性質(内角や外角)を視覚的に理解したり、分数や小数の計算をプログラムで行うことで、その意味や性質への理解を深めたりします。
- 理科: 電気の流れや回路の仕組みをシミュレーションしたり、センサーを使って明るさや温度に応じて動作を変えるプログラムを作成したりすることで、電気や物理現象への理解を深めます。
- 国語: 物語の登場人物の動きをプログラムで表現したり、敬語の規則性をプログラムで考えたりすることで、言葉の仕組みや使い方について学びます。
- 音楽: 音の高さや長さをプログラムで指定し、繰り返しの構造を活用して簡単なメロディやリズムを作成することで、音楽の仕組みや表現方法について学びます。
- 図画工作: 自分で描いた絵をプログラムで動かしたり、色の組み合わせや明るさをプログラムで変化させたりすることで、表現の幅を広げ、創造性を育みます。
- 総合的な学習の時間: 身近な社会課題(例:観光案内、節電、防災)を見つけ、その解決策を考える過程でプログラミングを活用し、探究的な学習を行います。
主に使用される教材
小学校のプログラミング教育では、子どもたちが楽しく学べるように様々な教材が活用されています。
- Scratch(スクラッチ): マサチューセッツ工科大学(MIT)が開発した無料のビジュアルプログラミング言語。ブロックをドラッグ&ドロップで組み合わせる直感的な操作で、ゲームやアニメーション、音楽など様々な作品を作成できます。多くの小学校で採用されています。
- Viscuit(ビスケット): 自分で描いた絵を動かせる、よりシンプルなビジュアルプログラミングツール。メガネという仕組みを使って絵に動きを与えます。低学年でも取り組みやすい教材です。
- micro:bit(マイクロビット): イギリスBBCが開発した教育用マイコンボード。LEDやボタン、センサーなどが搭載されており、MakeCodeなどのビジュアルプログラミング環境でプログラムを作成し、様々な電子工作や制御が可能です。
- Minecraft Education Edition(マインクラフト エデュケーション エディション): 人気ゲーム「マインクラフト」の教育版。ゲームの世界でブロックを組み立てるように、MakeCodeなどのビジュアルプログラミングで建築やキャラクター制御などを行い、楽しみながらプログラミングを学べます。
- ルビィのぼうけん: フィンランドのプログラマー、リンダ・リウカス氏によるプログラミング絵本。コードを使わずに、物語やアクティビティを通してプログラミング的思考の基礎を学ぶことができます。
- レゴ教材(レゴ®ブースト、レゴ®SPIKE™プライムなど): レゴブロックでロボットなどを組み立て、専用アプリでプログラミングして動かします。モノづくりとプログラミングを組み合わせた実践的な学習が可能です。
- アンプラグド教材: カードセットやボードゲームなど、コンピュータを使わずにプログラミングの概念を学ぶための教材です。

保護者が抱える不安とその解消法
プログラミング教育を受けた経験のない保護者にとって、子どもの学習をどう見守り、サポートすれば良いのか不安に感じるのは自然なことです。ここでは、保護者が抱きがちな主な不安と、その解消に向けた考え方を紹介します。
不安1:学校の授業の質に差があるのでは?
プログラミング教育は必修化されたばかりであり、教員のICT活用指導力や学校の設備環境には地域や学校によって差があるのが現状です。教員向けの研修は行われていますが、すべての先生が十分に指導できるとは限りません。また、1人1台端末の整備は進んでいますが、その活用度合いも学校によって異なります。
- 解消法: 学校の授業内容や進度について、学校説明会や懇談会などで積極的に情報収集しましょう。もし学校の授業だけでは不十分だと感じる場合は、家庭での学習や外部の学習機会(プログラミング教室、オンライン教材など)を検討するのも一つの方法です。
不安2:子どもが授業についていけるか心配
「うちの子はパソコンに触ったことがない」「プログラミングなんて難しくてついていけないのでは」と心配になる保護者もいるでしょう。しかし、小学校のプログラミング教育は、プログラミング言語の習得が目的ではなく、プログラミング的思考を育むことに重点が置かれています。
- 解消法: 小学校で使われる教材は、子どもでも直感的に操作できるビジュアルプログラミングツールが中心です。まずは家庭で一緒にパソコンやタブレットに触れる機会を増やしたり、Scratchなどの無料教材を試したりして、デジタル機器やプログラミングに慣れておくことで、授業への抵抗感を減らすことができます。また、授業でつまずいたとしても、それは学びの機会です。失敗を恐れず、試行錯誤することの大切さを伝えましょう。
不安3:親にプログラミングの知識がないけどサポートできる?
親自身がプログラミングの経験がない場合、「子どもに質問されても教えられない」「どうサポートすればいいか分からない」と感じるかもしれません。
- 解消法: 親がプログラミングの専門知識を持っている必要はありません。大切なのは、子どもの学びに関心を持ち、一緒に考え、励ます姿勢です。子どもが「できた!」と報告してきたら一緒に喜んだり、困っている様子なら「どこでつまづいたの?」「どうしたらいいと思う?」と一緒に考えたりするだけで、子どもは安心して学習に取り組めます。また、無料のオンライン教材や書籍などを活用して、親子で一緒にプログラミングに触れてみるのも良いでしょう。親が学ぶ姿を見せることは、子どもにとって何よりの刺激になります。
家庭でできるプログラミング教育のサポート方法
学校の授業に加えて、家庭でもプログラミング的思考を育むためのサポートができます。特別な知識や高価な教材がなくても、日常生活の中でできることはたくさんあります。
1. デジタル機器に慣れる機会を作る
プログラミング学習には、パソコンやタブレットなどのデジタル機器を使う場面が多くあります。小さいうちからこれらの機器に触れ、基本的な操作に慣れておくことは、学習をスムーズに進める上で役立ちます。
- 一緒に触ってみる: 子どもと一緒にパソコンで調べ物をしたり、簡単なゲームをしたり、絵を描いたりする時間を作りましょう。マウス操作やキーボード入力(タイピング)の練習も、楽しみながら行うのがポイントです。
- 目的を持たせる: ただ漫然と触らせるのではなく、「この情報を調べてみよう」「この絵を完成させてみよう」など、目的を持って取り組むように促しましょう。
- ルールを決める: デジタル機器の利用時間や、インターネットを使う際のルール(個人情報を教えない、知らない人と連絡を取らないなど)を親子で話し合って決め、安全に利用できるように見守りましょう。
2. 日常生活で「順序立てて考える」習慣を育む
プログラミング的思考の基本は、物事を順序立てて考えることです。これはプログラミングだけでなく、あらゆる学習や日常生活に役立つ力です。
- お手伝いや準備の手順を考える: 料理の手順、片付けの手順、明日の準備など、身近な活動を「まず何をしたらいいかな?」「次にどうする?」と一緒に考え、順序を確認してみましょう。
- 遊びの中で考える: ブロック遊びで何かを作る手順を考えたり、迷路の解き方を考えたり、ボードゲームの戦略を立てたりすることも、論理的思考の練習になります。
- 「なぜ?」「どうしたら?」を問いかける: 子どもが何かをしているときや困っているときに、「どうしてそうなるのかな?」「どうしたらもっとうまくいくと思う?」と問いかけ、自分で考えることを促しましょう。すぐに答えを教えるのではなく、ヒントを与えながら一緒に考える姿勢が大切です。
3. 子どもの興味を引き出し、成功体験を増やす
プログラミング学習を継続するためには、子ども自身が「楽しい」「もっと知りたい」と感じることが重要です。
- 好きなことと結びつける: 子どもが好きなゲーム、アニメ、キャラクター、乗り物、動物などとプログラミングを結びつけられる教材や活動を探してみましょう。ScratchやMinecraft Education Editionなどは、子どもの興味を引き出しやすい教材です。
- 小さな成功を褒める: プログラムが意図した通りに動いたとき、エラーを自分で解決できたときなど、小さな成功でも大いに褒めてあげましょう。「できた!」という達成感が、次の挑戦への意欲につながります。
- 一緒に楽しむ: 親も一緒にプログラミングに挑戦したり、子どもが作った作品を見て感想を伝えたりすることで、子どものモチベーションを高めることができます。

4. 地域の資源や外部の学習機会を活用する
学校や家庭での学習に加えて、地域の公共施設や民間のサービスを活用することも有効です。
- 図書館や公民館の講座: 地域によっては、図書館や公民館で子ども向けのプログラミング講座が開催されていることがあります。無料または安価で参加できる場合が多く、気軽にプログラミングに触れる良い機会になります。
- オンライン学習サイト・アプリ: 無料または有料のオンライン教材やアプリを利用すれば、自宅で好きな時間にマイペースで学習できます。動画で分かりやすく解説されているものや、ゲーム感覚で学べるものなど、様々な種類があります。
- プログラミングスクール: より体系的に学びたい場合や、専門的なサポートを受けたい場合は、プログラミングスクールを検討するのも良いでしょう。講師に直接質問できたり、他の子どもたちと一緒に学べたりするメリットがあります。体験会に参加して、教室の雰囲気や指導方法を確認することをおすすめします。
小学生におすすめの家庭学習教材
家庭でプログラミング学習に取り組む際に役立つ、おすすめの教材をいくつか紹介します。お子さんの年齢や興味、家庭の環境に合わせて選んでみてください。
ビジュアルプログラミング
- Scratch(スクラッチ): 無料で利用でき、Webブラウザ上で動作します。ブロックを組み合わせるだけで、ゲームやアニメーション、音楽など多様な作品が作れます。対象年齢は8歳~16歳ですが、ScratchJr(5歳~7歳向けアプリ)もあります。小学校の授業でも広く使われているため、予習・復習にも最適です。
- Viscuit(ビスケット): 無料で利用でき、スマホやタブレットでも手軽に始められます。自分で描いた絵を動かすことに特化しており、より直感的な操作でプログラミングの考え方を学べます。対象年齢は4歳からと低く、プログラミング入門にぴったりです。
ロボット・電子工作系
- embot(エムボット): ダンボールでロボットを組み立て、専用アプリでプログラミングして動かします。身近な素材を使うことで、モノづくりの楽しさも同時に味わえます。プログラミングレベルを5段階で調整できるため、初心者から経験者まで対応できます。
- mBot(エムボット): 車型のロボットを組み立て、ビジュアルプログラミングやテキストプログラミングで制御します。拡張パックで様々な形に変形させることができ、より発展的な学習も可能です。
- micro:bit(マイクロビット): 小さなコンピューターボードにプログラムを書き込み、LEDを光らせたり音を鳴らしたり、センサーを使った制御を行ったりできます。電子工作とプログラミングを組み合わせたいお子さんにおすすめです。
- レゴ教材(レゴ®ブースト、レゴ®SPIKE™プライムなど): レゴブロックで組み立てたロボットをプログラミングで動かします。遊び感覚で物理的な動きとプログラムの関連性を学べます。対象年齢や難易度に応じて様々なシリーズがあります。
ゲームベース
- Minecraft Education Edition(マインクラフト エデュケーション エディション): 人気ゲーム「マインクラフト」の世界でプログラミングを学びます。MakeCodeなどのビジュアルプログラミング環境を使って、建築を自動化したり、キャラクターを制御したりできます。ゲーム好きのお子さんがプログラミングに興味を持つきっかけになります。
絵本・カード・アンプラグド教材
- ルビィのぼうけん: プログラミングの概念を物語を通して楽しく学べる絵本です。コンピュータを使わずに、プログラミング的思考の基礎に触れることができます。
- アンプラグド教材: カードゲームやボードゲームなど、コンピュータを使わずに論理的思考や順序立てて考える力を養う教材です。親子で一緒に遊びながら学べます。
オンライン学習サイト・通信教育・スクール
- Progate(プロゲート): 初心者向けのオンラインプログラミング学習サイト。スライド形式で分かりやすく、ゲーム感覚で学べます。小学生高学年でテキストプログラミングに興味を持った場合などに適しています。
- 通信教育(進研ゼミ、スマイルゼミなど): 既存の教科学習に加えて、プログラミング学習のコンテンツを提供している場合があります。普段の学習と合わせて取り組みたい場合に便利です。
- プログラミングスクール: 専門の講師から体系的な指導を受けられます。対面式やオンライン式があり、カリキュラムや使用教材も様々です。体験レッスンなどを活用して、お子さんに合ったスクールを選びましょう。

まとめ:未来を切り拓く力を、親子で楽しく育もう
小学校のプログラミング教育は、単にコードを書く技術を学ぶのではなく、変化の激しい社会で必要となる「プログラミング的思考力」や「問題解決能力」「創造力」といった、普遍的な力を育むことを目的としています。
保護者の方がプログラミングの知識がなくても、心配する必要はありません。お子さんの学びに関心を持ち、日常生活の中で順序立てて考える習慣を促したり、一緒にデジタル機器に触れたり、様々な教材や外部の学習機会を上手に活用したりすることで、十分にサポートすることができます。
プログラミング学習は、子どもたちが「知りたい!」「やってみたい!」という好奇心を持って、試行錯誤を繰り返しながら「できた!」という成功体験を積み重ねていくプロセスそのものです。この経験を通じて得られる力は、将来どのような道に進むとしても、きっとお子さんの大きな武器となるでしょう。
ぜひ、親子で一緒にプログラミングの世界に触れ、楽しみながら未来を切り拓く力を育んでいきましょう。